第一想起は構築できるか?:BtoBで「最初に思い出されるブランド」になるための、カテゴリーブランディング実践ロードマップ
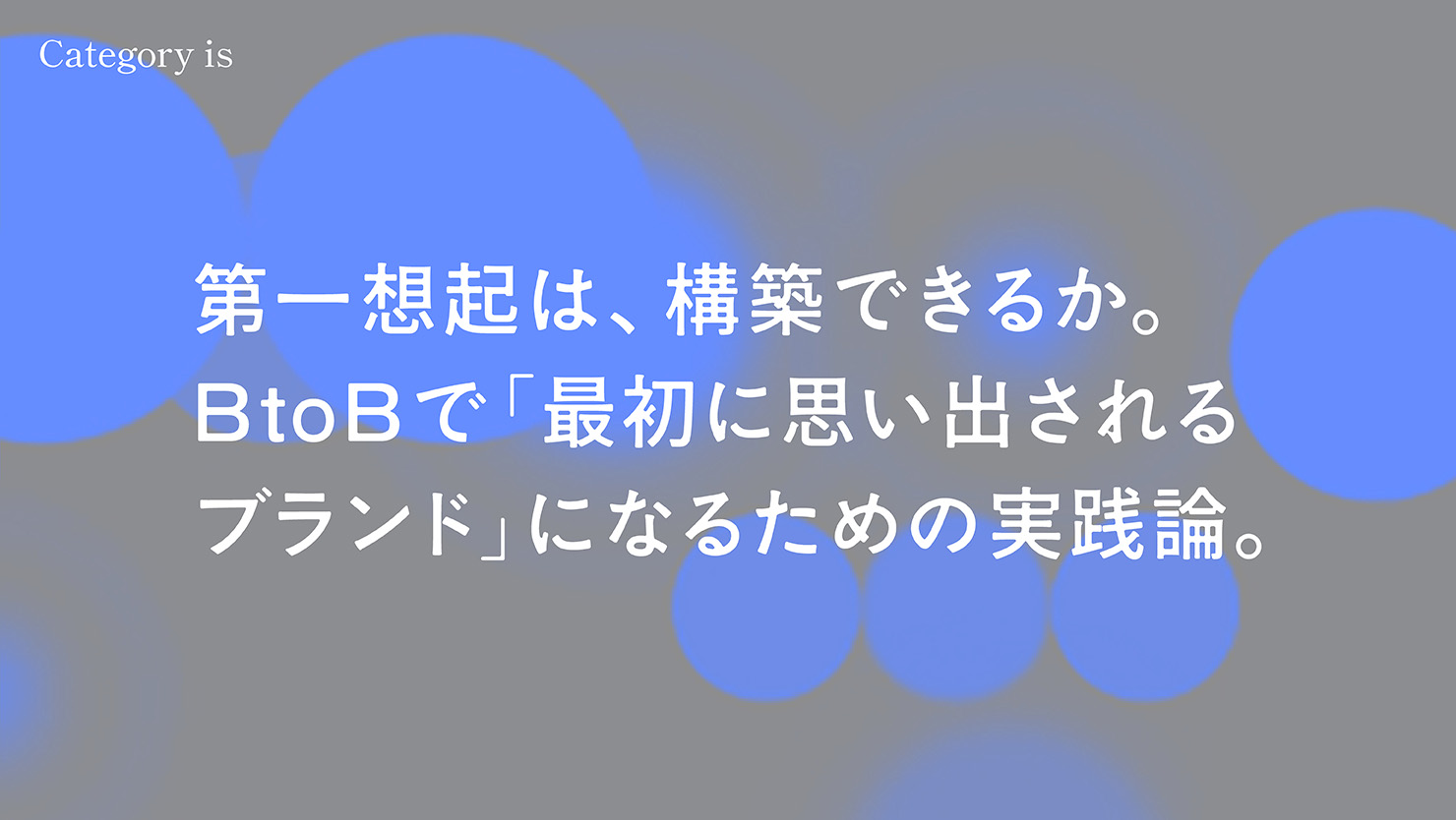
機能比較表のいち項目として、自社の名前が並んでいる。その光景に、疑問を抱いたことはないでしょうか。
価格、スペック、導入実績──。競合と同じ物差しの上で評価され、その差が僅かな数字でしかない状況。それは、自社だけが持つユニークな価値が、顧客に正しく届いていないことの証左に他なりません。「その他大勢」の一社として扱われ、熾烈な消耗戦を強いられる。BtoB市場において、これほど非生産的な戦いはありません。
この状況から抜け出す、本質的な一手が存在します。それは、比較検討が始まる「前」に、勝負を決めること。顧客が特定の課題に直面した瞬間、競合他社の名前が挙がるよりも先に、真っ先にあなたの会社を思い浮かべてもらうこと。
その究極のポジションこそが「第一想起」です。
第一想起は、偶然や広告の物量だけで生まれるものではありません。それは、自社のユニークな価値を核として、市場に新しい“認識”を創り出し、顧客の評価軸そのものをデザインする「カテゴリーブランディング」という戦略によって、意図的に構築されるものです。
比較される存在から、想起される存在へ。
それは、市場における自社の“意味”を再定義し、顧客の頭の中に新しい“常識”を打ち立てるという挑戦に他なりません。
そのための思考の深め方と、実践への道のりを、ここから共に探求していきましょう。
序章:なぜ、あなたの会社は「思い出して」もらえないのか?
機能比較の終焉:BtoB市場における「差別化」という幻想
そもそも、なぜこれほどまでに自社の価値を伝えることが難しくなったのでしょうか。その答えは、多くの企業が同じ場所で、同じルールで戦い続けているという、市場構造そのものにあります。
SaaS業界を例に取るまでもなく、ある企業が画期的な機能を追加しても、数ヶ月後には主要な競合が同様の機能を実装している光景はもはや日常です。技術の進化と情報の透明化は、機能やスペックによる優位性を極めて短期的なものにしました。それは、利益を削り合うだけの終わりなき消耗戦に他ならないのです。
一方で、買い手側もまた、溢れる情報の中で最適な選択をすることに疲弊しています。BtoB向けの比較サイトは一見便利ですが、そこで提示されるのは標準化された項目ばかり。結果として、各社の本質的な違いは見えにくくなり、「結局どこも同じに見える」という状況を助長しているのです。
血を流し続ける消耗戦:市場の95%を見過ごすという致命的な過ち
さらに深刻なのは、多くの企業がアプローチする対象を、自ら狭めてしまっているという事実です。
LinkedInの調査によれば、BtoB市場において「今すぐ買う」状態にある顧客は、全体のわずか5%に過ぎません。多くの企業が、この限られたパイを巡って熾烈な広告合戦や営業活動を繰り広げています。しかし、それは最も競争が激しいレッドオーシャンに、全力で飛び込んでいるに等しいのです。
持続的な成長の鍵を握るのは、まだ購入を具体的に検討していない、残りの95%という広大な潜在市場です。彼らがいつか課題に直面したとき、数多の選択肢の中から、あなたの会社を“最初に思い出してもらえる存在”になれているか。その状態を意図的に創り出すことこそが、現代のBtoB戦略の核となります。
問うべきは「違い」ではない。「想起」されるか、否かだ
これまでの議論が示すのは、既存の土俵の上で「違い」を訴え続けることの限界です。顧客は、その微細な違いを理解することに疲れ、もはや関心を払ってくれません。
真に問うべきは、全く別の問いです。
「顧客が特定の課題に直面したとき、あなたの会社は、そもそも選択肢として“想起”されているのか?」
そして、さらに重要な問いが続きます。
「想起されるとして、それは何番目なのか?」
この問いこそが、消耗戦から抜け出し、顧客の記憶という新しい戦場で主導権を握るための、全ての始まりとなるのです。
第1章:「第一想起」の再定義 – 顧客の記憶を制するということ
「想起」という言葉は、単なる認知度とは明確に区別されなければなりません。顧客の記憶におけるブランドの存在感は、一般的に3つの階層からなるピラミッド構造で理解されます。
想起のピラミッド:単なる認知(Recognition)と想起(Recall)の決定的な違い
- 土台:助成想起 (Brand Recognition)
ブランド名やロゴといったヒントを与えられた際に、「知っている」と認識できるレベルです。これは、比較検討の土俵に上がるための最低条件ですが、これだけでは選ばれる理由にはなりません。 - 中腹:純粋想起 (Brand Recall)
「〇〇のカテゴリーで思い浮かぶブランドは?」といったヒントなしの質問に対し、自発的にブランド名を思い出せるレベルを指します。純粋想起されるブランドは、顧客が能動的に解決策を探し始める際の「検討集合(Consideration Set)」に入るために不可欠です。 - 頂点:第一想起 (Top-of-Mind Awareness, TOMA)
そして、ピラミッドの頂点に立つのが「第一想起」です。これは純粋想起の中でも、特定のカテゴリーやニーズに対して「真っ先に」思い浮かぶ、ただ一つのブランドを指します。
頂点に立つ唯一の存在:第一想起(Top-of-Mind Awareness)とは何か
第一想起とは、単に「一番目に思い出される」という順序以上の意味を持ちます。それは、顧客の頭の中に、特定の課題解決者としての独自のポジションを確立し、そのカテゴリーにおける顧客の心の中の占有率、すなわち「マインドシェア」を最も高く獲得している状態の証左です。
顧客がある課題に直面したとき、「それなら、あの会社だ」と、競合他社に先駆けて、無意識レベルで自社の名が結びつく。この状態こそが第一想起であり、ブランド構築における究極の目標と見なされているのです。
なぜBtoBでこそ第一想起は生命線となるのか
BtoCにおいても第一想起は重要ですが、特にBtoB市場において、その価値は決定的な意味を持ちます。
複雑な意思決定プロセスを貫く「信頼の代理指標」
BtoBの購買は、現場担当者、上司、情報システム部、経理部、役員など、多数のステークホルダーが関与する「複数意思決定」が基本です。それぞれの立場から異なる評価軸で製品を判断するため、議論は平行線を辿りがちです。
この複雑な迷宮において、購買担当者は無意識のうちに自身の負担を軽減しようとします。情報収集にかかる「認知コスト」と、選択を誤るかもしれない「信頼リスク」。この2つの重圧を最小化する最も効果的な手段が、「この分野なら、まずあの会社に聞けば間違いない」という第一想起ブランドに頼ることなのです。
第一想起ブランドは、購買担当者にとって、この認知コストと信頼リスクを劇的に低減させるための「思考のショートカット」として機能します。それは、そのカテゴリーにおける品質や信頼性を保証する「信頼の代理指標(Proxy for Trust)」としての役割を担うのです。
価格競争から脱却し、利益の「正のスパイラル」を生む力
第一想起を獲得したブランドは、競合他社に対して圧倒的な競争優位性を持ちます。顧客がそのブランドを指名買いする傾向が強まるため、売上に直接的に貢献するだけでなく、ブランドへの信頼から顧客は価格に対して寛容になります。
これにより、価格競争からの脱却や価格プレミアムの設定が可能となり、収益性が向上します。そして、その利益をさらなる製品改善やブランド価値向上に再投資することで、競争力を高めるという「正のスパイラル」が生まれるのです。
このように、第一想起への投資は、単なるマーケティング施策ではありません。それは、事業全体の収益構造を根底から改善するための、極めて重要な戦略的投資なのです。
第2章:想起を制するための戦略的青写真 – 「権威性」「対話」「ビジョン」
では、どうすればこの強力な戦略的資産である「第一想起」を構築できるのでしょうか。それは、断片的な施策の寄せ集めではなく、体系的かつ長期的な視点に立った戦略によって実現されます。その核となるのは、「権威性の構築」「継続的な対話」「ビジョン主導」という3つの柱です。
戦略の柱1:権威性の構築 – あなたは何の専門家として記憶されたいのか
BtoBの購買担当者は、合理的な判断を下すために信頼できる情報を求めています。このニーズに応え、「信頼できる専門家」としての地位を確立する最も強力な手法が「ソートリーダーシップ」です。
ソートリーダーシップとは、特定の分野で革新的なアイデアや深い洞察を発信し、業界や顧客を啓蒙・先導していく活動を指します。優れたソートリーダーシップは、顧客がまだ認識していない潜在的な課題に光を当て、単なるベンダーではなく「信頼できるアドバイザー」としての認識を醸成します。ある調査によれば、B2Bの意思決定者の73%が、企業の能力を判断する上でソートリーダーシップを信頼できると回答しており、第一想起へと繋がる強力なドライバーとなるのです。
戦略の柱2:継続的な対話 – 記憶を風化させない一貫した顧客体験
どんなに強力なメッセージも、一度伝えただけでは忘れ去られてしまいます。BtoBの長期にわたる検討期間において第一想起を維持し続けるためには、様々な顧客接点(タッチポイント)で一貫したブランド体験を提供し、継続的に顧客の記憶に働きかける「対話」が不可欠です。
ウェブサイトの使いやすさから、営業担当者の専門的な提案、カスタマーサポートの迅速な対応まで、あらゆる接点でのポジティブな顧客体験(Customer Experience)は、顧客の心に好意的な印象を刻み込み、第一想起の強力な基盤となります。ロゴやメッセージのトーン&マナーを全てのチャネルで統一し、顧客が購買プロセスのどの段階にいても、一貫した価値を提供できる体制を築くことが求められます。
戦略の柱3:ビジョン主導 – 機能(What)ではなく、存在意義(Why)を語るということ
製品の機能やスペック(What)だけで差別化を図ることは、ますます困難になっています。このような状況で決定的な差を生み出すのが、企業の存在意義(Why)、すなわち「ビジョン」です。
自社が「何をしているか」ではなく、「なぜそれをしているのか」「どのような社会を実現したいのか」を語るビジョン主導型ブランディングは、顧客の合理的な判断だけでなく、感情的な共感を呼び起こします。例えば、サイボウズは単なる「グループウェアメーカー」ではなく「チームワークあふれる社会を創る」というビジョンを掲げることで、「働き方改革」の旗手として認知されています。
このようなアプローチは、ブランドを単なるツール提供者から、価値観を共有する「パートナー」へと昇華させます。この強い共感が、機能比較を超えた強固な第一想起を形成するのです。
第3章:戦略の土台を築く:「カテゴリーブランディング」が第一想起への最短路である理由
「権威性」「対話」「ビジョン」。これらは第一想起を構築するための強力なエンジンです。しかし、これらの活動を単なるバラバラな施策ではなく、一つの強力な戦略として機能させるためには、何が必要なのでしょうか。その答えが、すべての活動の「土台」であり「旗印」となるカテゴリーブランディングなのです。
「何において」思い出してもらうのか? – 旗の無い場所に、人は集まらない
ソートリーダーシップを発揮するといっても、「何についての」専門家なのか。ビジョンを語るといっても、「どのような未来を」目指すのか。その問いに答える、全ての活動の“旗印”が必要です。
カテゴリーブランディングとは、既存の市場で戦うのではなく、自社のユニークな強みを基に、新しい市場を定義し、顧客に新しい認識を提示する戦略です。それは、「〇〇といえば自社」と思い出してもらうための、「〇〇」という部分を自ら創造する行為に他なりません。
カテゴリーブランディングが3つの戦略(権威性・対話・ビジョン)を束ねる理由
3つの戦略は、カテゴリーブランディングという土台の上で初めて、真の相乗効果を発揮します。
- 権威性は、自らが創造したカテゴリーの「定義者」であり「第一人者」として発揮されます。
- 対話は、その新しいカテゴリーの価値を、あらゆるタッチポイントで一貫して伝え続けるための活動となります。
- ビジョンは、そのカテゴリーが顧客や社会にもたらす、より良い未来の物語そのものとなるのです。
これら3つの戦略は、カテゴリーブランディングによって一つのベクトルに束ねられ、競合が模倣不可能な、持続的な第一想起の源泉となるのです。
事例分析:彼らは「何」の第一想起を、いかにして獲得したのか
この戦略を巧みに実践し、第一想起を獲得した企業は少なくありません。
- HubSpot: 「インバウンドマーケティング」というカテゴリーの創造と支配
HubSpotは、自社製品を売り込む前に、まず「インバウンドマーケティング」という新しい概念そのものを市場に提唱し、教育することに注力しました。ブログやeBookといった膨大な量の高品質な教育コンテンツを無償で提供し続けることで、彼らは「インバウンドマーケティング」というカテゴリーの代詞となり、そのカテゴリーに関心を持つほぼすべての潜在顧客を自社のエコシステムに引き込むことに成功したのです。 - Salesforce: 「SFA/CRM」の定義と、ビジョンによるエコシステムの構築
Salesforceは、単なるCRMツールではなく「SFA(営業支援システム)」というカテゴリーを創出し、その代名詞となりました。『Customer 360』というコンセプトのもと、顧客に関わるあらゆるデータを統合するプラットフォームを提供し、巨大イベント『Dreamforce』などを通じて顧客やパートナーを巻き込み、共に成長するエコシステムを形成しています。彼らは製品を売るだけでなく、顧客の「成功」を支援するパートナーとしての第一想起を確立しています。 - 東海バネ工業: 「特殊バネの駆け込み寺」という関係性カテゴリーの深化
オーダーメイドのバネを製造する東海バネ工業は、オウンドメディア「ばね探訪」で、自社製品ではなく、顧客企業の事業や成功の物語を深く掘り下げて紹介し続けています。これは、自社を「黒子のパートナー」として位置づけ、究極の顧客中心主義を貫くことで、「特殊な仕様のバネで困ったら、まず東海バネ工業に相談する」という、技術者の頭の中の絶対的な第一想起を確立した事例です。
第4章:カテゴリーブランディング実践ロードマップ:第一想起を獲得する3つのステップ
では、具体的に何から始めればよいのでしょうか。カテゴリーブランディングを通じた第一想起の獲得は、以下の3つのステップに分解できます。
STEP 1:顧客の「課題」を再定義する – 「御用聞き」から「課題定義者」へ
すべての始まりは、顧客の「認識(パーセプション)」を変えることからです。そのためには、顧客の「御用聞き」になるのではなく、彼ら自身も言語化できていない本質的な課題をこちらから定義し、提示する必要があります。
陥りやすい罠は、自社の製品ありきで課題を後付けしてしまうことです。これを避けるには、「失注顧客」に話を聞くのが有効です。なぜ選れなかったのか、そこには自社が見落としている顧客のリアルな認識が隠されています。そして、「今何に困っていますか?」ではなく「魔法が使えたら、どんな状態が理想ですか?」と未来の視点で問いかけ、理想から逆算して本質的な課題を炙り出すのです。
STEP 2:自社のユニークな強みを掛け合わせる – 価値は“発見”するものである
次に、新しい価値提案を創出します。特許技術のような目に見える資産だけでなく、組織文化、独自のプロセス、顧客との関係性といった無形の資産を含めて棚卸しし、それらを掛け合わせることが重要です。
「うちには特別な強みはない」と思い込むのは、最も避けたい思考停止です。長年の慣習や成功体験が、新しい視点での強みの発掘を阻害することもあります。これを乗り越えるには、「よそ者」の視点を借りましょう。中途入社や異動直後の社員に「我が社のユニークな点は?」と聞けば、社内の常識を疑うヒントが得られます。そして、複数の強みを掛け合わせることで、誰も提供していないユニークな提供価値を発見するのです。
STEP 3:カテゴリー名を創造する – 新しい市場に“名前”を与えるということ
最後に、再定義した課題と独自の強みを統合し、それを象徴する新しい「カテゴリー名」を創造します。この名前は、顧客があなたを思い出すための、強力な記憶のフックとなります。
重要なのは、その言葉が独りよがりな造語ではなく、顧客がその提供価値(ベネフィット)を正しく想像できるか、という視点です。Sales Marker社が提唱した「インテントセールス」のように、言葉自体が価値を示すものが理想です。確信が持てない場合は、複数のネーミング案で小さな市場テストを行い、最も響く言葉を選び抜くというプロセスが不可欠です。
第5章:想起を可視化し、組織を動かす
カテゴリーブランディングは、目に見えない顧客の「記憶」を対象とするがゆえに、その成果を可視化し、組織的な活動へと繋げることが極めて重要です。
あなたの会社の「想起率」を測るには? – 市場調査から指名検索まで
第一想起は目に見えない資産ですが、適切な手法でそのレベルを可視化できます。最も正確な方法は、ターゲット顧客を対象とした市場調査です。『「〇〇」と聞いて、思い浮かぶ企業名を、思いつく順に全てお書きください』といった純粋想起を問う質問を実施し、その中で最初に記述されたブランドを「第一想起ブランド」として集計するのです。
しかし、市場調査はコストと時間がかかります。より機動的にブランドへの関心度を測るための、強力な代理指標(Proxy Metrics)が存在します。
指名検索は、顧客の心に火が灯ったサイン
その最も分かりやすい兆候が、「指名検索」の増加です。
顧客が検索エンジンで企業名や製品名を直接入力する「指名検索」のボリュームは、ブランドへの関心度や想起の強さを測る、極めて強力な代理指標です。指名検索をするユーザーは、すでにそのブランドを認知し、具体的な情報を求めているため、購買意欲が高い傾向にあります。この指標を月次でモニタリングすることは、ブランディング活動の健康状態を知るための、簡易的かつ効果的なバロメーターとなるのです。
カテゴリー創造は、組織を動かす「物語」になる
最後に、カテゴリーブランディングという活動がもたらす、もう一つの重要な側面についてお伝えします。それは、単なるマーケティング戦略に留まらず、社内の全部門を巻き込み、一つの方向に推し進める「共通の物語」になるという点です。
例えば、「“インテントセールス”という新しい市場を創り、顧客の営業活動を根底から変える」という強力な物語は、以下のような効果を組織にもたらします。
- 営業部門に、価格競争から脱却し、「価値」を語る誇りを与える。
- 開発部門に、「何を作るべきか」という明確な北極星を示す。
- 採用部門に、「我々が何者で、どこへ向かうのか」を魅力的に伝え、思想に共感する人材を引き寄せる。
- 全社員に、日々の業務が社会にどのような新しい価値を生み出しているのかという、仕事への意義と一体感をもたらす。
カテゴリー創造とは、社外に向けた旗印であると同時に、社内に向けた羅針盤でもあるのです。
終章:比較される存在で終わるか、想起される存在になるか
機能や価格での比較競争から抜け出し、「第一想起」を獲得すること。それは、自らが市場の新しい「常識」や「評価軸」そのものを創り出し、顧客の未来を定義していく、崇高な事業戦略です。
思い出される存在になるための戦いは、顧客の頭の中から始まります。その戦いに、スペック表や価格表は必要ありません。必要なのは、顧客の本質的な課題を見抜く洞察力と、自社の価値を信じて新しい旗を立てる勇気だけです。
あなたの会社が消えたとき、最も困るのは誰か?
この記事の最後に、あなたのビジネスの核に迫る、一つの問いを投げかけたいと思います。
あなたの会社がこの市場から消えたとき、一体誰が、何に最も困るのでしょうか?
その答えこそが、あなたの会社だけが提供できる本質的な価値であり、あなたが創るべきカテゴリーの核となるはずです。