「カテゴリーは思想から生まれる」──Sales Markerが挑んだ“インテントセールス”という革新

営業の現場では長年、顧客のニーズを把握できないまま大量のアプローチを繰り返す“手探り営業”が当たり前とされてきました。
そんな状況に革新をもたらしたのが、株式会社Sales Marker CEOの小笠原羽恭氏です。彼が生み出した新しい営業手法「インテントセールス」は、“営業される側とする側が本当に価値を感じ合える関係をつくる”という思想を出発点に生まれました。
本記事では、インタビュアーの塩口が小笠原氏に、インテントセールス誕生の裏側から、カテゴリー戦略の真髄を聞きました。
出演者

Interviewee株式会社Sales Marker 代表取締役 CEO
小笠原 羽恭
新卒で野村総合研究所に入社し、新規事業開発に従事。その後、戦略コンサルティングファームにて、新規事業戦略・営業変革・DX推進プロジェクトを多数リード。
2021年に株式会社Sales Marker(旧:CrossBorder株式会社)を創業。国内初の「インテントセールス」を実現するソリューション『Sales Marker』を開発・提供し、BtoB企業の営業・マーケティング活動における”顧客起点”の成長戦略の確立を支援。インテントセールスの第一人者。
さらに2025年、スーパーエージェント『Orcha(オルカ)』をリリース。営業に限らず、企画、マーケティング、人事、経営など多様な職種の業務において、意思決定・資料作成・タスク実行・記録管理などをAIが一気通貫で支援することで、生産性と成果を飛躍的に高める革新をもたらしている。
2023年「Forbes 30 Under 30 Asia List」選出、2024年「The Wall Street Journal Next Era Leaders」受賞。一般社団法人生成AI活用普及協会(GUGA)協議員。著書に『AIエージェント時代の成長戦略『インテントセールス』 – 組織の成果を最大化するための革新的アプローチ』(翔泳社)がある。

“ニーズが見えない世界”からの脱却が、営業の常識を変える世界を創造する

塩口 まず、小笠原さんがインテントセールスというカテゴリーを設計しようとした時、最初に見えていた潜在課題は何だったのでしょう?
小笠原氏 営業の現場では、顧客のニーズを事前に知る手段がほとんどありませんでした。多くの企業が潜在ニーズを探しながらも答えが見つからず、半ば諦めていたんです。
そんな中、アメリカでは「セールスインテリジェンス」という領域が存在していました。セールスインテリジェンスは、AIやテクノロジーを活用して顧客データや行動履歴を分析し、最適なタイミングでアプローチできる仕組みです。これが日本でも実現できない理由はないと考え、挑戦を始めました。
塩口 なるほど、小笠原さんのキャリアはもともと営業マンとしてスタートしたわけではないと思うのですが、セールスインテリジェンスやインテントセールスに興味を持った原体験は何かあるのでしょうか?
小笠原氏 私は元々エンジニアとして社会人のキャリアをスタートしたんです。プロダクトを創造し、コンテストで優勝したこともありました。ですがお金を払ってでも解決したいニーズには届いておらず、作ったプロダクトは良い方向に行かなかったんです…。
過去の経験から“ニーズを探し続ける”という日々が始まりました。2年から3年の間『ニーズはどうしたら発見できるのか…』と自問自答する毎日でした。当時を振り返るとビジネスパーソンというよりは、現場のエンジニアなので一切わからず…
塩口 なるほど…「どこかにニーズがあるはずだ!」と思い、プロダクトへの想いもあるから一人称目線になりがちになるというか…。
小笠原氏 そうなんです。なので自分の人生をかけて、ニーズがわからないという課題を解決したいと思いSales Markerをリリースしました。
言葉が市場を動かした──「セールスインテリジェンス」から「インテントセールス」へ
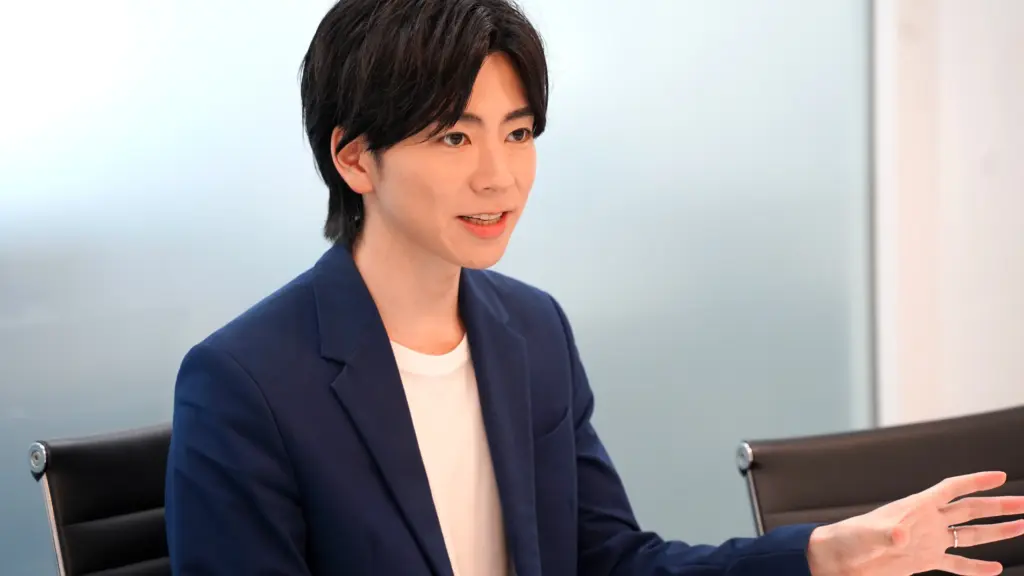
塩口 潜在課題を明確化する方法として、セールスインテリジェンスを浸透させようと思ったとのことですが、初期の苦労はどのような点でしたか?
小笠原氏 そもそも、インテリジェンスが日本人には馴染まないという課題がありました。イベントで登壇しても、30人ほどの参加者のほとんどが「Sales Markerの名前もセールスインテリジェンスという言葉も覚えていない」状態で、後の反応は「“興味や関心がわかるやつ”って面白いですね」という曖昧な反応ばかりでした。
塩口 なるほど…「ビジネスインテリジェンス」も一時期、日本で注目を浴びていましたが浸透しきらなかったですよね。
小笠原氏 そうなんですよ。そこで思い切って「インテントセールス」という言葉に変えたところ、空気が一変しました。「インテントセールスをうちでも導入したい!」と、声が多く上がるようになったんです。
塩口 なるほど。その「インテント」という言葉自体は当時あまり馴染みがなかったと思いますが、どうやって人々の記憶に残るようにしたのでしょうか?
小笠原氏 「セールス」という言葉が入っていたことで、営業に関わるものだと認識してもらいやすかったのが大きいですね。さらに、インテントセールスの仕組みを映像で見せて、グラフなどで“ニーズが可視化される瞬間”を直感的に理解してもらえるようにしました。
この“見える化”が革新的だと多くの方に感じてもらい、言葉と体験がセットで広がったのだと思います。もし文面や音声だけで説明していたら、ここまで浸透しなかったでしょう。
塩口 やはりビジュアルで理解できるインパクトは大きかったんですね。
小笠原氏 そうですね。創業当初から“ニーズを視覚的に見せる”ことにはこだわっていました。ビジュアル化されて初めて、顧客は「本当にニーズがある」と実感できるようになるので、ここにはかなり力を入れてきました。
市場を生む言葉を定義する──小笠原氏が語る啓蒙初期の戦略
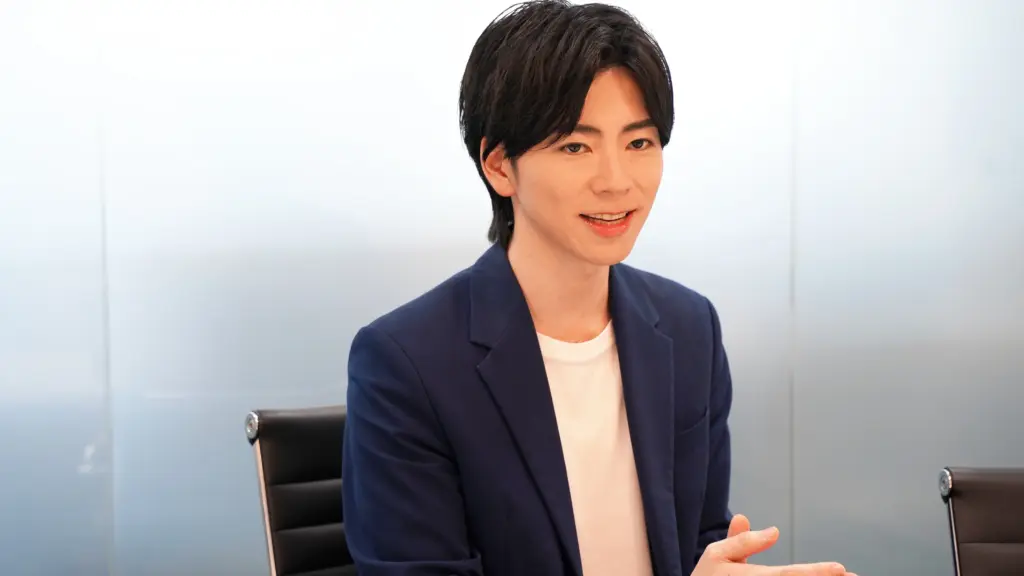
塩口 啓蒙初期に意識的に取り組んでいたことはありますか?
小笠原氏 そうですね、主に2つの取り組みに注力しました。1点目は、市場を作ることです。そして2点目は、言葉の定義を明確にすることに注力しました。特に2点目の言葉の定義の明確化にはかなりの時間をかけましたね。
私たちのソリューションを明確化した生まれたのが、「ウェブ検索行動からわかるニーズに基づき、タイムリーにアプローチする新しい営業手法」という文章です。
市場をつくるためには、言葉が統一されていることが不可欠だと思いました。そのためメンバーが、同じフレーズとソリューションの核をブラさないで、外部に話せるようにする必要があると思い、言葉を作り込みました。
塩口 なるほど…言葉の定義はどのように作り込んでいったのでしょうか?
小笠原氏 言葉を定義するまでのプロセスは泥臭い道のりでした。マーケティング界隈でよく言われているようなフレームワークに当てはめると、綺麗な言葉は生まれるけどそこに想いや、自分たちの原体験、気持ちが反映されないように感じたんです…誰かの言葉を借りてきたような違和感を感じるというか….。
塩口 その感覚わかるかもしれません…自分たちの想いから、言葉を紡ぐ必要がありますよね。
小笠原氏 そうなんです。なので、毎週3日~4日間、夜9時から深夜まで議論を重ね、全員が同じ言葉で説明できるようになるまで磨き込みました。既存のセールステックでは拾えなかった“ウェブ検索行動から見えるニーズ”こそ新しい価値だと考え、それを旗印に市場を作っていったのです。
塩口 ありがとうございます。一つ気になったのですが、その言葉を定義する前の段階で、既存のカテゴリーや既存のセールステックが整理されていないことについて、まずは定義し直したり、テーブルに並べて整理するようなことも考えられましたか?
小笠原氏 まさに、そのプロセスは避けて通れませんでした。「ウェブ検索行動からわかるニーズ」というのが、既存のセールステックやカテゴリーの定義を見直すことに直結しました。
これまでのセールステックでは、商談が発生して初めてCRMに情報が蓄積されるという構造が前提になっており、そもそもその中にニーズが含まれているかどうかすらわからない。プロパティに「ニーズ」という項目があっても空欄のままで、実質的には活用されない――そんな課題が長らく存在していました。
つまり、企業が対象とする顧客(ユーザー)に聞いても得られなかったニーズが、我々のデータベースを活用すれば、ニーズを明確にできる―― その結果、ディファレンスが生まれクライアント様から弊社を選んでもらえるようになったのだと考えています。
塩口 なるほど…それ以外で啓蒙フェーズで取り組まれていたことは何かありますか?
小笠原氏 記事広告を出したり、ビジネスメディア『PIVOT』に出演させていただいたり、認知度を高めるために露出を増やしました。あとは、サービス紹介の動画を作ったり、本を出版したり―― 執筆に1年以上かかりましたが、地道な努力も相まって、私たちが定義した市場が広がり、お客様の役に立っていることが定量数値としても見え始めていきました。
カテゴリーが形になった瞬間──競争優位性と市場浸透の舞台裏
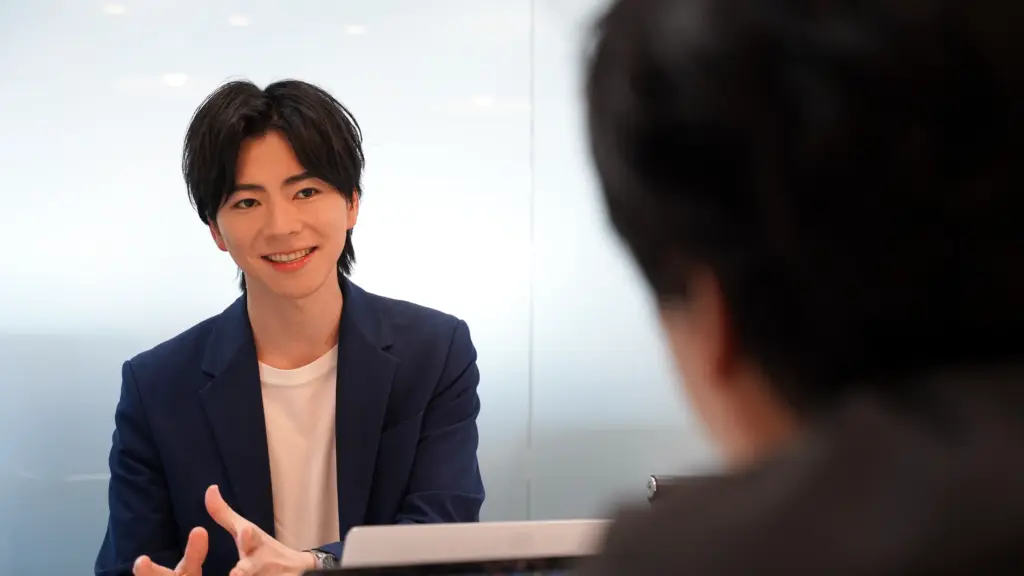
塩口 徐々に成果が生まれていったとのことですが、カテゴリーが形成されたと実感したのはいつですか?
小笠原氏 イベントでこれまでお会いしたことのないような方から「インテントセールスを導入したい!」と声をかけられるようになった時。そして、「SalesTech Landscape(セールステック領域におけるサービスプロバイダーを俯瞰的にまとめた図)」におけるセールステックのカオスマップに海外の大手企業と並んでソリューションが掲載された時です。
この2つの転換期から、検索ボリュームもゼロに近かったところから2桁3桁と急増しました―― 確実に市場に根付き、カテゴリーが生まれたのを実感したんです。
塩口 インテントセールスが世の中に広がると、競合が生まれてきますよね。その時に、競合との差別化はどのように築かれたのでしょう?
小笠原氏 私たちは「データベース×インテント×アプローチ=競争優位性」だと思っています。私たちの強みは、この三要素をすべて揃えている点です。他社はデータベースの活用だけだったり、インテントとは名ばかりで適切なデータが揃っていなかったり、AI系のサービスではアプローチのみになっていてデータを活用できていなかったりするケースが多い印象があります。
私たちは数千のファーストパーティデータと50億レコード規模のサードパーティデータを活用し、精度の高いインテント検知と、アプローチを実現しているのが強みです。
塩口 なるほど…インテントセールスが「Sales Marker」とイコールで認識されるようになったことで、受注率やチャーン率にどんな変化がありましたか?
小笠原氏 大きな変化がありました。まず営業の入り口では、インテントセールスを理解していただいているため、そもそも論から説明する必要がなくなり、1回目の受注までのハードルが大幅に下がりました。
また出口の部分では、「ツールを使えるか、使えないか」ではなく、「インテントセールスをどう続けるか」という議論に変わりました。結果として、より目指すべきセールス像に近づけるようになり、継続率も大きく向上しました。
塩口 コア顧客は戦略的に定義した上で、受注率が上がったのでしょうか?
小笠原氏 はい、ターゲットを明確化したことで成果が出ました。ただし、そもそも検索ニーズがない業界や商材も存在します。検索されないものはインテントを検知できません。そこで、新規事業向けには、検索数を増やしてニーズを検知できるようにする「Marketing Marker」を立ち上げました。
既存事業の高度化には「Sales Marker」、新規事業には「Marketing Marker」と、ツールを使い分けています。プロジェクトごとにインテントジェネレーションのホイールが回っているかを徹底的にチェックし、成果が出ていない企業には改善アドバイスを行うようにしています。
また弊社は、ポイントソリューションではなく、トータルソリューションとして企業の課題をご支援させていただいているのも特徴です。
塩口 なるほど!あのソリューションは、すごくわかりやすいですよね。価値が顧客に伝わりやすい印象を受けます。
エンタープライズ市場への挑戦と認知獲得の戦略

塩口 BtoBのエンタープライズ領域に展開する際、当初は認知が低かったと思いますが、課題はどのように乗り越えてきたのでしょうか?
小笠原氏 特に大きな役割を果たしたのは、動画と書籍の存在です。インテントセールスという新しい概念は、言葉だけではなかなか伝わりにくいと感じたため、実際の仕組みや成果を可視化できる動画を活用しました。また、書籍という形で思想や事例を体系的にまとめて発信しました。
また、Forbesや日経新聞、PIVOTなどのメディア露出も追い風になりました。第三者に紹介いただくことで、まだ認知がなかった大手企業にも「安心できるサービス」として認められ、導入につながるケースが増えたのです。
さらに、データの扱いにも細心の注意を払いました。「Clean Data Policy(クリーンデータポリシー)」を掲示し、企業が安心してデータを預けられる体制を整えたことが、信頼を得る大きな要因になったと思います。
塩口 やはり露出は戦略的に取り組んでいたんですね!
小笠原氏 はい。インテントセールスという概念を世の中に広めるためには、私自身が前に出て発信し続ける必要があると思っていました。
例えばテスラがここまで認知されているのは、イーロン・マスク氏が前面に出て語ったからこそです。世界を変えるようなイノベーションは、CEOが旗を振らなければ起きない。そう考え、露出の多さは意図的に作ってきました。
カテゴリーを超えた成長戦略──複合ソリューションで広げるインテントの可能性
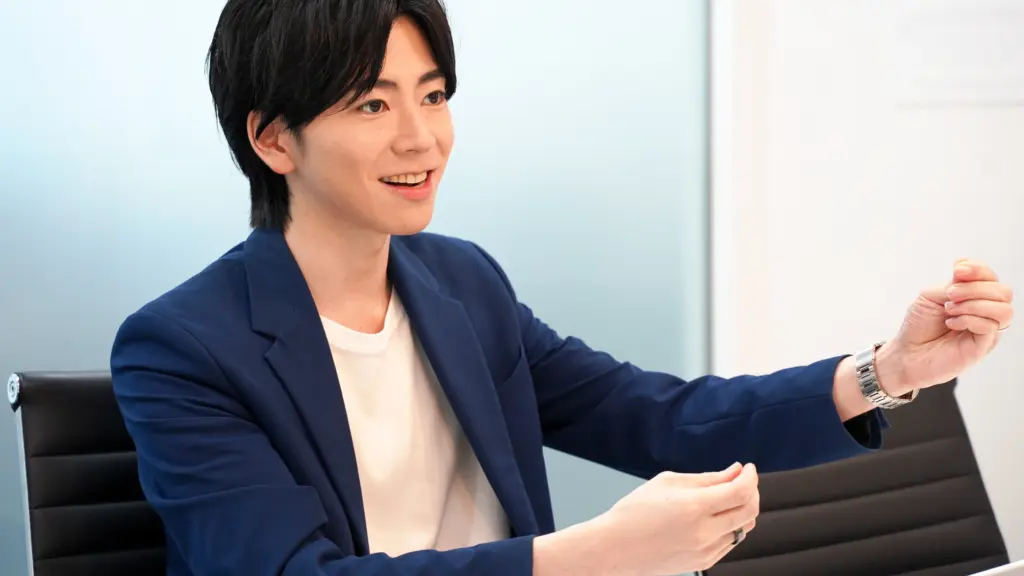
塩口 インテントセールスの概念が浸透し、一定の認知を得た後、スタートアップが成長の壁にぶつかるケースも多いと感じます。御社では、その壁をどう突破したのでしょうか?
小笠原氏 私たちは、カテゴリーを単一のサービスに限定せず、課題を起点に「コンパウンド戦略(複数のカテゴリーにまたがる要素を組み合わせた複合的な概念や製品を指す)」を採用しています。
具体的には、インテントを検知できない市場に対しては「Marketing Marker」を展開し、検索数を増やすことで新たなニーズを生み出す仕組みを作っています。また、営業人員が不足している企業には「Recruit Marker」を導入し、採用から営業力強化までを支援します。
これらのソリューションを「インテント」という共通の軸で繋げることで、マーケティングからセールス、リクルーティングまでが一気通貫で回るホイールを構築しています。
プロジェクトごとにこのホイールが回っているかを確認し、成果が最大化するようアドバイスや改善を重ねていく。こうした仕組みによって、インテントセールスだけでは届かなかった層にも価値を提供でき、事業の成長をさらに加速させることができました。
塩口 カテゴリーが広がっても、「インテント」という軸はブラさなかったんですね。
小笠原氏 そうですね。セールスの会社なのか、マーケティングの会社なのか、リクルーティングの会社なのか……カテゴリーを複合化すると、どうしても外からの見え方が分かりにくくなるリスクはあります。
すべてのソリューションをインテント起点で業務を効率化するという思想のもとに置くことで、複数のプロダクトがあっても一本の軸でつながるようにしています。結果として、それぞれのサービスが独立しながらも融合し、外部から見ても“インテントの会社”として認識いただける状態を保てていると思います。
カテゴリー設計がもたらした社内変革──本質的な会話が生まれる組織へ

塩口 社内でもインテントの会社という共通認識が生まれたと思うのですが、組織で何か変化はありましたか?
小笠原氏 大きく3つあります。まず1つ目は、社内メンバーの“プロダクトの認識”が変わったことです。初期は「ツールです」と説明する社員も多かったのですが、今は皆が「インテントセールスを実現するサービスです!」と言えるようになりました。この言葉の変化は大きく、ツールと聞くと数万円の単価感で捉えられがちですが、私たちはしっかり工数とコストをかけて成果にコミットするサービスです。インテントセールスとしての共通言語が社内に根付いたことで、提供価値を正しく共有できるようになりました。
2つ目は、対顧客の場面です。お客様に「インテントセールスを成功させるポイントは何ですか?」と聞かれた際、社員が迷わず「3つのポイント」を説明できるようになりました。『「必要なKGI」「KGIの担保に必要なKPI」「明確なUSPの定義」の3つが鍵です』と答えられるようになりました。これにより議論の質が変わり、プロジェクトの再現性が格段に上がりました。
3つ目は、自分たち自身への認識です。単なる機能を売る会社ではなく、インテントセールスという新しい行動習慣をインストールしてもらう会社だという自覚が浸透したことです。
塩口 やはり、プロダクト単体を売るのではなく「インテントセールスを導入するかどうか」という概念をお客様に選んでもらっているんですね。行動習慣を変える選択肢として提供しているのが強いなと思いました。
小笠原氏 はい、それが一番大事だと思っています。単なるマーケティングトレンドではなくて、行動習慣を変え、より質の高い事業を構築するための習慣だと考えています。
思想がカテゴリーを生む──小笠原氏が語るリーダーの条件

塩口 ここまでインタビューにお付き合いいただき、ありがとうございました!最後の質問です。カテゴリーを作れるスタートアップリーダーと、そうでないリーダーの違いは何だと思いますか?
小笠原氏 一番の違いは“思想があるかどうか”だと思います。単に利益を追求したいだけの人や、ツールを作ること自体が目的の人、あるいは海外のアイデアをそのまま日本に持ち込む“タイムマシン経営”では、新たなカテゴリーは生まれません。
私たちは、営業する人とされる人が互いに感謝し合える世界をつくりたいと考え、そのために何が課題で、何が重要なのか、どうすれば実現できるのかを徹底的に考え抜いたからこそ、新たなカテゴリーを生み出すことができたのです。思想がなければ不可能だと思います。

塩口 なるほど…考え深いですね。インテントが分かるとか、ニーズが分かるっていうことが、当たり前ではないからこそ、その価値を誰よりも理解しているんだと思います。
小笠原氏 そうですね。もう一つお伝えしたいのは、多くの方が「どこかにニーズがあるはず!」と思い込んでいますが、私は基本的に「ニーズは存在しない」という前提で考えています。
ニーズは掘り起こし、見つけ出すものなんです。
もし本当にニーズがなければ、そのプロダクトには価値がない可能性もありますし、ニーズの捉え方自体を根本から見直す必要があるかもしれません。だからこそ、ニーズを生み出すことこそがイノベーションの本質だと考えています。
塩口 なるほど。見えていないインサイトを掘り起こし、価値を創造することこそが、世の中にとっての本当の価値なんですね。
小笠原氏 はい。そして、もう一つ重要なのは、新たなカテゴリーを生み出すためには「従来よりも10倍優れたもの」を作る必要がある、という点です。
『Startups in 13 Sentences』の著者・ポール・グレアムも言っていましたが、「1.5倍や2倍程度では市場は動かない。10倍の価値を提供できてはじめて価値が生まれる」――つまり、10倍の価値を提供できて初めて新しいカテゴリーが生まれる―― そして10倍の価値があるソリューションを提供するには思想が必要ですし、それを具現化するプロダクトが必要です。
Sales Markerを導入した結果、商談数が10倍に増えたり、商談率が劇的に改善したりと、誰が見ても明らかな成果が出て初めて、その思想が意味を持ち、カテゴリーとして定着していくのです。

塩口 これまでのお話を聞いていると、ビジネスパーソンが見えてないインサイトニーズをどう生み出すかに向き合っていることを強く感じます。また カテゴリーは、やはりイノベーションとセットなんですね。マーケティングだけでは生まれない、そんな印象を受けました。
小笠原氏 その通りです。フォードの有名な話がありますよね。「もっと速い馬が欲しい」と人々が望んでいた時代に、彼が生み出したのは“3倍速い馬”ではなく、まったく新しい「車」でした。私は、カテゴリーを創るとは、まさにそういうことだと思っています。
塩口 つまり、カテゴリーは既存の延長ではなく、これまでにない価値を生み出すイノベーションが必要だということですね。
小笠原氏 はい。カテゴリーはマーケティングの産物ではなく、イノベーションの結果として生まれるものです。新しい市場を作りたいのであれば、まずは誰もが驚くような価値を創り出すことが重要です。独自の思想を持ち、既存の枠組みを打ち破り、従来よりも圧倒的に優れたものを提供する。そうした挑戦の先にこそ、本当のカテゴリーが生まれるのだと思います。
